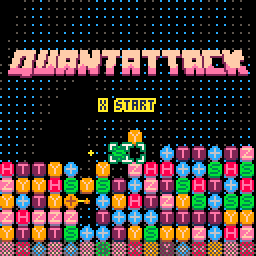ゲームに必要な「面白さ」の設計
TEXT by Akihico Mori
シリーズ累計60万本以上を売り上げている世界的なヒット作『タイムボム』を量子的に進化させたボードゲーム『タイムボムQ』。編集担当として制作に携わったアークライトの野澤邦仁と、監修を行った大阪大学教授・藤井啓祐が、ゲームと量子の関係について語り合った。ゲームと量子のよい関係は、まず面白いこと。ゲームに必要な「面白さ」はどのように設計されるのか。
Designing the Fun Factor in Games
Designing the Fun Factor in Games
タイムボムQ 量子世界を舞台に敵味方を探るチーム戦カードゲーム。観測者が他者の手札をめくり、「突破カード」ならQポリス、「ノイズンカード」ならNボマーズが勝利に近づく。嘘と駆け引き、運の要素で何度も盛り上がれる。
量子の入口としてのゲーム
ーー『タイムボムQ』はどのようにして生まれたのでしょうか?
野澤:もともと弊社アークライトから『タイムボム』というゲームを発売していて、ありがたいことにとても好評をいただいています。その基になったインディーズ版から数えて、10周年を迎えたことから、新作を作ろうという話が出ていました。
そう考えていたときに、量子ソフトウェアのスタートアップ、QunaSysさんから「量子コンピューターを題材にしたボードゲームを作れないか」というお話をいただきました。ボードゲームを通じて量子の仕組みを学び、興味を持ってもらえるようなものにしたいというご相談でした。
『タイムボム』は、プレイを進める中で隠された正体が徐々に明らかになっていくという仕組みを持っています。量子力学における「観測によって状態が確定する」という性質と相性が良いと感じ、ゲームのテーマとして適していると思いました。
ーー実際のゲーム制作はどのように進んでいったのでしょう?
野澤:実際の制作に入る前に、明確にしておかなければと考えたのは、『タイムボムQ』を「量子を学ぶもの」にするのか、それともその手前の「量子に興味を持ってもらうもの」にするのか、という点でした。
もし「量子を学ぶ」ことを目的にしてしまうと、どうしても教育的な達成目標を組み込む必要が出てきます。しかしそうすると、ゲームとしての面白さと、量子の振る舞いの正確性との間でジレンマが生じます。正確性を優先すると難しくなりすぎて退屈なゲームになってしまう。一方で、面白さを優先すると、どうしても物理的な正確さから外れてしまう。こうした葛藤が必ず起きると分かっていたので、最初の段階でQunaSysさんと徹底的に議論しました。
結果として、今回は「量子に興味を持ってもらうもの」にしようという結論に至りました。
藤井:量子コンピューターの勉強で最初から「アダマールゲートはこう作用します」と行列を書いて説明すると、多くの人が挫折してしまいます。しかしルールとして「同じ色のものは消える」として、それによって何かのゴールを達成するという面白さを与えると、自然にアダマールゲートを使えるようになり、理解も進む。ゲームは量子力学の理解におけるハードルを下げる、非常に有効な手段だと思います。
野澤:すでに勉強したい人は自分で学び始めているものなんですよね。そうではなく、「量子」という言葉は聞いたことがあるけれど実際にはよく分からない、という中高生や、進路を考え始めた高校生などに、「そういえば量子ってあったな」「面白そうだな」「調べてみたいな」と思ってもらえるようなきっかけを提供することを目指しました。
制作では、量子の振る舞いとゲームの仕組みがぶつかった場合には、まずゲームとしての面白さを担保して、それから量子的に腑に落ちるように調整をかける、という順序を徹底しました。その代わり、ゲーム内のカード名やグラフィックデザインには量子力学に関連した言葉や記号を多く採用しました。「この名前はどういう意味なんだろう?」「このデザインって意味があるのでは?」と気になってもらうための引っかかりとして、あえて専門用語を散りばめています。
ゲームデザインは、「面白さ」ありき
ーー『タイムボムQ』はゲームとしても面白いですが、教育でも使えそうですよね。
野澤:実はゲームの構成を二段階に分けています。まずは純粋にゲームとして楽しんでもらい、「量子をテーマにしたゲームって面白かった」とポジティブな体験を持って帰ってもらう。その後、学びたい人には、ワークショップや座学などで「ゲーム中に登場した名称や効果は実は量子のこんな性質を表している」と解説する場を設けられるように構成しています。ゲームだけで完結させず、遊びと学びを分けることで、参加への心理的ハードルを下げるようにしました。
ゲーム中ではカード名や効果を何度も口にするため、自然と用語が記憶に残ります。その状態で後から「実はこのカードの効果は量子のこういう性質なんです」と説明を受けると、すでに体験として理解している分、納得しやすい。そういう流れで「遊んでから学ぶ」仕組みを設計しました。
ーー藤井先生もゲームをつくっていますよね? 万博の「エンタングルモーメント」で試遊もできます。
藤井:「クアンタアタック」というゲームで、ゲームの仕組みとしては、いわゆる「落ちゲー」であり、同じパネルやブロックをつなげると消えるというシンプルなルールです。ただし、実際には量子コンピューターの基本ゲートをモチーフにした操作になっています。
量子コンピューターのアルゴリズムは、最終的にシンプルな基本ゲートの組み合わせに分解して実行します。例えば、ある演算を分解したときに、無駄な操作が出てきた場合はそれを省き、回路をできるだけ簡略化していきます。「クアンタアタック」は、そうしたゲート操作のルールを、ゲームとして体験できるようにしたものです。最初は何も考えずに同じ色のブロックをつなげて消していくだけですが、遊んでいるうちに「この3種類を組み合わせると高得点になる」というルールに気づきます。自然に繰り返し遊ぶことで、量子ゲートの操作に慣れていく仕組みになっています。
現在までに延べ2万人ほどがプレイしていて、X上では攻略法や消し方の議論も活発です。プレイヤーが自発的に「なぜこの組み合わせで消えるのか」を考え、理屈を説明し合う様子は非常に面白い現象です。
QuantAttack(クアンタアタック) 大阪大学QIQBの藤井啓祐副センター長が考案したアクションパズルゲーム。量子コンピュータで実際に使われるゲート操作がゲームのルールに組み込まれている。
ーーふたりとも、量子を扱ったゲームをつくっているけれど、「面白い」というところに基軸を置いてゲームデザインをしている点は共通していますね。
野澤:まず何より「ゲームとして面白い」ことが大切だと思っています。これまでにも量子をテーマにしたゲームはいくつかありましたが、多くはゲームとしての面白さよりも、量子へのリスペクトを優先してしまっているんです。
そもそも面白くなければ多くの方にはプレイしてもらえません。ゲームの面白さがあってこそ、その先に「もっと知りたい」という興味が生まれるんだと思っています。量子の正確性を優先しすぎると、どうしてもルールを覚えること自体が勉強になってしまい、結果的に量子をすでに理解している人しか遊べないゲームになってしまうと思い、それでは本末転倒だと考えました。
大切なのは、理論を理解してから実践するのではなく、まず体験があり、その後に「なぜそうなるのか」という理論が後からついてくる流れです。ゲームだからこそ、その順番が可能になると考えました。
藤井:今回は『タイムボム』というヒットしたゲームをベースにしているのがいいと思いますね。やっぱり、王道のゲームや成功しているゲームには、普遍的で魅力的な要素があります。そうした土台に乗っかることは、とても重要だと思います。ゲームとしてあまりに新しすぎると、ルールを理解する段階でプレイヤーに大きな負担がかかってしまいますから。
実際、『QuantAttack(クアンタアタック)』も、基本ルールは、任天堂の『パネルでポン』や『テトリス』、『ぷよぷよ』などの「落ちゲー」と共通するものです。
ーー今回の『タイムボムQ』の中で、一番「これはうまくいった」と思える仕掛けは何ですか?
野澤:個人的に一番面白いと思っているのは、「モツレン」というキャラクターです。このゲームでは、正義陣営と悪の陣営に分かれて進行しますが、特定の枚数「モツレン」がめくれてしまうと、効果でプレイヤーの陣営が秘密裏に入れ替わってしまうんです。
制作チームの中でも、「量子もつれっぽい!」と盛り上がりました。ゲームとしても非常にドラマを生むカードで、途中まで正義陣営としてプレイしていたのに、最後の最後で悪の陣営になってしまうこともある。プレイヤーはその可能性も踏まえた戦略を考えなければならず、従来の『タイムボム』にはなかった新鮮なスパイスになっています。
藤井:面白いですね。ちなみに、「Qポリス」という名前も良いですよね。
野澤:そうなんです。「量子警察」という言葉をもじってつけた名前で、制作チームの中でもかわいいと評判でした。ある分野に厳格な人たちを「○○警察」と呼んだりしますが、そのニュアンスを取り入れた遊び心のあるネーミングにできたと思います。
藤井:GPUももともとはゲーム用に発展しましたが、その結果としてAIを支える重要な技術基盤となりました。同じように、量子コンピューターにとってゲームは、将来を切り拓くビジョンの重要な一部になるのではないかと思います。
野澤邦仁(のざわ くにひと)
1987年 神奈川県 横浜市生まれ。東京工芸大学 芸術学部(現ゲーム学科)企画分野一期生。デジタルゲームのプランナーやボードゲームショップの店員を経て、2015年から株式会社アークライトに在籍。ボードゲーム編集者として80作以上に携わる。主な編集担当作(一部は原案も)は、『ito』『タイムボム』『ナナトリドリ』『タイガー&ドラゴン』『六華』など。
藤井啓祐(ふじい けいすけ)
2011年3月京都大学大学院工学研究科 博士課程修了。博士(工学)。2019年4月から、大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻、教授。大阪大学量子情報・量子生命研究センター副センター長、理化学研究所量子コンピュータ研究センター量子計算理論研究チームチームリーダー等を兼任。量子コンピュータのソフトウェアベンチャー、株式会社QunaSys、最高技術顧問。専門分野は量子情報、量子コンピューティング。特に、量子誤り訂正、誤り耐性量子計算、測定型量子計算、量子計算複雑性、量子機械学習。